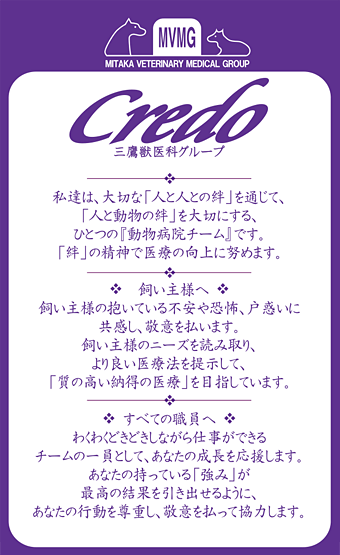人と動物の絆
人と動物の絆、絆を重視した獣医療
伴侶動物への愛情は、あなたの心と身体に愛情があふれます。

人類の歴史と共に、常に動物の存在がありました。現代では、その動物たちは家畜から犬や猫へと変化し、さらにその犬や猫は、家の外での役目から住居の中での役目、すなわち家族の一員としての役割、いわゆるコンパニオン・アニマル(伴侶動物)へと変化しています。
この伴侶動物たちは、人間の良き仲間として、家族に多くの恩恵を与えています。そのためには、正しいしつけと社会生活に必要なマナー、そして病気に対する看護が必要となります。
現在は「心の時代」と呼ばれていますが、古今東西を問わず、昔から人と人との関係が世の中の構成において重要視されており、このことが社会の基本構成となっています。現代社会は、ある意味でストレスとの戦いの社会ともいえます。そのような社会において、人と動物の関係が改めて見直されつつあります。
伴侶動物の存在は、社会に潤いを与えてくれるものです。

最近では、人間の医学においても「Psycho-somatic medicine(心身医学)」が見直されつつありますが、その際に大きな役割を果たす存在が、伴侶動物です。ヒトと動物との絆の関係は、単に伴侶動物の飼育者に健康上の恩恵をもたらすだけでなく、人間に自然への回帰の心を芽生えさせます。
ヒトと動物との自然なふれあいは、子どもたちの脳の発育にも有益であり、「命の大切さ」や「思いやりの精神」が芽生え、動物とのふれあいを通じて、気づきのある教育の機会を増やすことができます。
また、高齢者が伴侶動物を飼育することで、孤独感や寂しさから解放されたり、親戚や近所との付き合いのきっかけとなったりして、良好な人間関係の構築に役立つことが証明されています。

最近の動物病院でよく言われている「絆を中心とした獣医療」とは、動物の病気の状態を正しく把握しつつ、長年寄り添ってきた家族の希望や、動物の性格・個性を尊重しながら、その動物と家族との絆を大切にする獣医療です。
これは単に「病気」だけを治すのではなく、家族の希望に沿った方法で「病人」を治す、すなわち病気とともに動物の心身の状態にも配慮しながら治療を行うことを目指しています。そのため、動物の医療においても避けて通れないのが、動物病院における「インフォームド・コンセント(説明と同意)」の重要性です。
動物病院は、伴侶動物の健康を守ることによって、家族全体の健康を守ることにもつながります。伴侶動物が持つ力を信じ、その力を存分に発揮してもらいましょう。そのためにも、年に2回の健康診断を受けることをおすすめいたします。
伴侶動物への愛情は、
あなたの人生に100の恩恵をもたらします。
100の恩恵 -
- 伴侶動物は、精神的ストレスから開放を促進する。
- 触り、話しかけると、痛みに対しての軽減効果を認める。
- 共にいる仲間として、感情の起伏を抑える働きがある。
- 連れ添う仲間として、心の安定に関与する。
- 伴侶動物は、子供たちの情操教育に役立つ。
- 緊急災害時、火事等を知らせて飼い主を助けることもある。
- いろいろなリハビリテーションにも貢献できる。
- 伴侶動物は、介助の役目もはたすこともある。
- 伴侶動物がいると、寂しさからの開放に役立つ。
- 伴侶動物のふれあいを通じて人間関係が良くなる。
- 伴侶動物を飼育する家族は、離婚率がより少なくなる。
- 伴侶動物との会話を通じて、夫婦の中が良くなる。
- より会話する機会が増え意思の疎通ができるようになる。
- 飼い主の運動(犬と散歩)する機会が増す。
- 生活を共にするので、日常生活が規則的になることがある。
- 伴侶動物との生活は、生きがいを感じる機会が増える。
- 仲間として生活するので、幸福感を感じやすくなる。
- 伴侶動物との生活は、血圧が安定する作用がある。
- 伴侶動物とふれあいは、心拍数がより安定する。
- 心筋梗塞等の心臓病に罹りにくく、進行も遅くなる。
- 伴侶動物とのふれあいで、コレステロール値が下がる。
- 伴侶動物とのふれあいで、中性脂肪が下がる。
- 伴侶動物とのふれあいで、病気からの回復の促進。
- 伴侶動物がいると、手術後の回復の促進。
- 伴侶動物との生活で、怒りからの回復が早い。
- 米国で医療費1.2%(65歳以上の医療費)の削減との報告。
- 英国で2.0%(65歳以上の医療費)削減との報告。
- 健康のために良いことが多い。(アニマルセラピー)
- 子供と時からいるとアレルギーが少なくなる。
- 犯罪の被害者になる恐怖感が少しでも減少する。
- 伴侶動物がいれば、犯罪に会う機会が減少する。
- 伴侶動物との生活で、病気で入院する率が減少する。
- 伴侶動物とのふれあいで、自閉症の治療効果として期待できる。
- 伴侶動物がいることで、自然と接する機会がふえる。
- 伴侶動物との共生は、地球環境を考える機会がます。
- 伴侶動物のそのしぐさや動作は、多くの笑いを生む。
- 伴侶動物との生活の、その思い出は独立心を生じる。
- 伴侶動物といることで、感覚としての刺激を感じる。
- 伴侶動物の存在は、自身以外によい環境を生み出す。
- 伴侶動物への訓練は、視覚障害者への助けとなる。
- 伴侶動物への訓練は、聴覚障害者への助けとなる。
- 伴侶動物への訓練は、身体障害者への助けとなる。
- 伴侶動物との生活は、孤独を感じる割合が低くなる。
- 伴侶動物とのふれあいは、ユーモアのセンスをより持つ。
- 伴侶動物がいると、帰る家を意識することが多くなる。
- 伴侶動物と共にいると、豊かな愛情がわいてくる。
- 伴侶動物がいれば、責任のある立場を自覚する。
- 伴侶動物がいると、感情のはけ口を持つことになる。
- 伴侶動物に話しかけると、話を聴いてくれる相手ができる。
- 伴侶動物の存在で、自身が価値のある人間と自覚できる。
- 伴侶動物との生活は、家族同士の結束が強くなる。
- 伴侶動物の存在は、人以外の平和的共存に貢献できる。
- 伴侶動物の存在は、自慢できる家族いると言うことである。
- 伴侶動物と共にいることで、世界で一つの価値を見出せる。
- 伴侶動物といると、育てる本能を発揮できる。(特に幼児)
- 伴侶動物の存在は朝目覚める、明確な理由ができる。
- 伴侶動物との生活は、自身の体内時計を自覚しやすくなる。
- 暖かくふわふわしているので触ると気持ちよくなる感覚が得られる。
- 手先の触覚は脳と関係があり、言語の発達に良い。(特に幼児)
- 伴侶動物がいない子供に比べて、いる子供は学校の成績がよい。
- 伴侶動物がいると寿命が長くなるとの報告がある。
- 伴侶動物との散歩は、新陳代謝が良くなることがある。
- 伴侶動物との散歩は、肥満の解消に役立つことがある。
- 伴侶動物とのふれあいは、脳性麻痺に有効な手段。(特に幼児)
- 伴侶動物は医師の指導で、動物介在療法として医療に貢献できる。
- 伴侶動物は、動物介在活動として医療に貢献できる。
- 生と死について、あらためて考える機会を得ることがある。
- 伴侶動物とのふれあいは、計算能力の向上の手段となる。(特に幼児)
- 伴侶動物とのふれあいは、記憶力の向上に手段となる。(特に幼児)
- 訓練によって犯罪の防止に役立てることができる。
- 伴侶動物の存在は、悩みごとを一時的にせよ、解消してくれる。
- 伴侶動物は身体的機能の改善に役立つことがある。
- 痴呆を遅らせ、改善の傾向に向かうことも可能である。
- 不審者を知らせ、飼い主の安全に役立つくとがある。
- アルツハイマー病の予防と進行を遅くするのに有効な手段。
- 食べる姿をみて、その心地よさに、食欲も増す効果あり。
- 水を飲む動作を見て、自身も水を飲む機会が増える。(特に高齢者)
- 伴侶動物の行動や習性をみて、いろいろ考えることで学習能力を増す。
- 伴侶動物の健康管理を考えて、自身の健康管理も考える。
- 伴侶動物に与えられたら、与え返す心が芽生える。
- いつも見張られている(観察の天才)ので、生活に張りが出る。
- 褒めると喜ぶので、褒めて育てることを人生でも学ぶことができる。
- 伴侶動物の誕生からの高齢への過程で、生命の尊さを知る機会が増す。
- 叱って教えるのは、信頼関係が壊れることを学ぶことができる。
- 伴侶動物自身は生涯、自立できないので、慈悲に心が芽生え優しくなる。
- 伴侶動物と同じ部屋に寝ることにより、より安心して睡眠ができる。
- 伴侶動物とのふれあいで、飼い主自身の感情表現が豊かになる。
- 伴侶動物とのふれあいで副交感神経の活動が増し、免疫機能が向上する。
- 伴侶動物とのふれあいにて、飼い主の体温が増加して、健康に寄与する。
- 唾液のアミラーゼ活性が低下するので、ストレス等の興奮の抑制に貢献。
- 伴侶動物の名前を繰り返す呼ぶことにより、脳の働きが良くなる。
- 伴侶動物との生活は、喘息と鼻炎に対して感受性を低くすることがある。
- 伴侶動物にふれあうと抑うつ状態になることが減少する。(特に高齢者)
- 刑務所における伴侶動物の存在は、静穏さを保ち、更生の機会を増す。
- 伴侶動物がいると、時間の周期や流れに対して自覚する機会を増す。
- 伴侶動物との共生はアスペルガー症候群の進行の遅れと改善に役立つ。
- 伴侶動物と共にいると、他の人達との争い事の確率が低下する。
- 伴侶動物との出会いは、人生の出会いと同じ意味で感動を生む。
- 一部の伴侶動物は、飼い主の癲癇の発作を感知する能力がある。
- 一部の伴侶動物は、地震等の天災の危険を予知する能力がある。
一般社団法人 ペットフード協会「笑顔あふれる、ペットとの幸せな暮らし」 のお知らせ(PDF版)よりopens a new window
伴侶動物の飼育には、このように良い事例や報告が数多くあります。ただし、年齢によって効果には違いがあり、特に幼児や高齢者に効果が見られる項目もあります。
また、犬と人間の愛情表現には違いがあります。人間にとって歯を見せることは「にっこり笑うサイン」ですが、犬にとっては威嚇のサインとなります。一方で、犬が尾を振ることは、愛情の表現です。このように、表現方法には前後の違いがあるため、注意が必要です。
ちなみに、犬は英語で「Dog」と書きますが、これを逆にすると「God(神)」という言葉になります。しかし、それにちなんで過度に甘やかして育てることは避けるべきです。
なお、この「100の恩恵」については、現時点ですべてが科学的に証明されているわけではありません。
では伴侶動物がいる欠点はどうでしょうか?
これらの問題はある意味では、利点ともなりうることもありますが・・・・
- アレルギーや伝染病の原因となりうる可能性がある。
- 排尿、排便の処置する必要がある。
- 食事の世話とかの看護する人が必要となる。
- 健康維持や病気にて、医療費が掛かる。
- いろいろな事故(転倒等)の原因となりうる。
- いろいろな問題(騒音等)の原因となる。
- 死亡した時に、あまりに切なく悲しい。