飼鳥の臨床
これから述べる飼鳥は、特に断わらない限りセキセイインコについての記述である。なぜならば、我々の病院のデータによると、飼鳥の約60%をセキセイが占め、文鳥が約25%でその他が約15%だからである。
飼育・管理・給餌法の重要点
飼鳥における疾病の診断と活療を知る以前に、臨床家は飼育、管理、給餌の方法の基本を知らなければなりません。一度いろいろな成書を読んでおくことが必要です。
ここでは特に診察をしていて、思いつくことを述べてみますと、まず初めに餌は皮付きの混合餌を与えることが必要です。むき餌の混合はカラがとび散らないのと、減りぐあいがよくわかるので、便利のようですが、本来鳥は皮をむいて食べるように噛ができていますので、多くの鳥は皮付きの方を好みます。むき餌は皮付きに比べて腐りやすく、古いものは死んだ餌で病気の原因にもなります。
また、むき餌は、うす皮がとれて粉になったヌカや、種子の中にあって将来、芽となる部分の胚芽があまりありませんので、栄養の面でも皮付きよりすぐれていません。実際に脚弱症、卵づまり、軟卵症などになる鳥は皮付きよりむき餌を食べている鳥に多く発症します。むき餌は普通艀化後25~30日ごろから皮付き混合と、半々に混ぜて使用し、皮付きを鳥がよく食べるようになったら与えるのをやめます。
しかしながら、むき餌は病気で噛が変形してカラを取ることができなくなった鳥などの場合には例外として与えなければなりません。 次に餌と水の関係ですが、水は艀化後25~30日頃から餌入れに入れて与えます。早くから水を与えていた鳥は、栄養も水と共に排出されてしまい、脚弱症などの病気の発症が多くなります。
アワ玉は普通艀化後25~30日頃まで与える餌ですが、いつまでもよく食べるからと言って与えていると、栄養が不足してきます。アワ玉はヒナ用の餌と発情用の餌であり、病鳥には強制給餌の餌としても使われます。
小鳥にはカルシウムが必要なことは言うまでもありません。補給にはイカの甲とボレー粉がありますが、どちらが好きかは鳥によって違いますので両方を与えてやるのがよいでしょう。
病鳥はもちろんのこと、普段の健康を維持するために獣医師が処方を推めるとよい2つの代表的な薬品の使用法は以下の通りです。
| AD3E剤 (トリミックス、工一ザイ) |
原液を水で等量にして、その2倍液を新鮮飲料水20~30ccに対して1滴の割合で毎日与える。 |
|---|---|
| ヨード剤 (複方ヨードグリセリン) |
甲状線異形成を予防するため、ヨードグリセリン2溶を蒸留水28容に加えたものを、週1回1滴新鮮飲料水30ccに加える。ヨードは化学的に活性なので、飲水には他の製剤を加えず、遮光にして冷蔵庫保存とする。 |
| 採光の問題 | できるだけ日光浴をさせる。午前中(やわらかい日ざしの時)2時間は必要です。多くの小鳥は、ビタミンD3の自然供給源である直射日光を奪われています。窓ごしの日光では、この必須ビタミンは供給されません。 |
|---|---|
| 安静 | 静かな環境で飼う。この事はその鳥を見ればだいたいその環境がわかるほどです。特に病鳥はケージ内に閉じ込め、十分回復するまでたっぷり睡眠をとらせる。鳥はケージが暗ければ日中でも眠ります。病鳥には12時間ぐらい必要です。 |
| 保全 | 鳥かごはできるだけ大きいもので飼って下さい。かごの大小は鳥の生命線です。又烏は常に清潔にして飼わなければなりません。不潔にするとすぐ病気になったり、ダニを寄生させることになります。 |
| 保温 | 夏は涼しく風通しの良い所、冬は暖かい所が必要です。飼い鳥の適温は20~22℃で、10℃まで低下すると体力を消耗しますが、この事は、運動量(かごの大きさ)と餌の質に大きく影響します。 |
| 食餌 | 鳥は味やにおいよりも外観によって選択される傾向があり、多くの食物から鳥に自由に選ばせることが良いのです。以下に示すような食餌を入れた餌コップを並べて鳥の種類によって選択して給餌すれば良い。
|
診察の前に必要な事柄
飼主に小鳥の状態を相談されたら?
飼主は初めに電話をかけて、私の小鳥が病気なのか?またその診断および治療法はどうするのか?を尋ねてくることがあります。そんなときには、どんなささいなことでも、それが起こっているのかを調べるために、飼主にその状態をよく聞きだし、診察が必要と思われたら、小鳥の病気は思ったほどより症状が進んでいることがあるので、できるだけ早く診察を受けるようにすすめることが重要である。
そして鳥を診てからでなければ、多くのことがわからないことをよく飼主に説明する。特に飼主が小鳥屋等で、すでに飲み水に薬を入れてある場合などは、なおさらである。犬や猫と比べて小鳥の場合は、治療が遅れればそれだけチャンスが少なくなることをよく説明する。
飼主が動物病院に鳥を連れて来ることになったら、どのように指示をすべきか?
動物病院で働くだれでもが、飼主からの電話の際に次のような事柄について説明し、指示できることが重要である。
- 飼育されていたそのままの籠ごと、連れて来ること。
- 便の状態等を調べるため、籠を掃除しないで持って来ること。
- 水は全部捨ててから、水入れはそのままの位置にして持って来ること。
- 籠を毛布等で被せてすきま風が入らないようにし、つとめて寒さから守るように工夫すること。
- もし鳥が傷ついていたり、ひどく弱っていたり、意識障害がある場合には、とまり木を低くしてぶらんこを除くこと。
- もしなにか使用した薬品・食品があれば、過去のものでも全部もって来てもらうこと。
- 時間予約をしてもらうこと。
電話で指示できる応急処置(テレフォンアドバイス)
もし飼主がなにかの都合で、どうしてもすぐには病院での治療が受けられない場合や、病院に来るまでの間の処置として、飼主の飼育の経験度や、熟練度によって、次の様な指示を与えて少しでも治療が成功するチャンスを高めることができる。
1. 一般的な応急処理
a.25~30℃に暖める。なんであれ、鳥は暖めることから始める。日光、電球、電気ストーブ、ヒーター、コタツなどが使用できる。
b.毛布で籠を被せる。できれば電気毛布がよい。
c.0.2gのアスピリンを160mlの水に溶かして、1時間ごとに4回まで経口的に1滴投与する。もし薬品が入手できればのことだが、薬局にての分配も可能と思われる。
d.静かな所に置いてやる。病鳥は十分な休息が必要で、そこはまた安全で、鳥の落ち着くところでなければいけない。
e.仲間の鳥の鳴き声が聞こえる所。病鳥はしばしば、仲間の鳥の声が聞こえるとそれにつられて、エサを食べようとしたりするものである。
2. 嘔吐をしている鳥
ミネラルオイル(入手できなければサラダオイルにても可能)を1滴飲まし、そ嚢をやさしく2~3回マッサージする。30分たったらもう一度くり返す。
3. 中枢神経系の障害
手でエサをできるだけ食べさせ、暖かいミルクや蜂蜜をスポイトでゆっくり飲ませる。
4. 下痢
重湯あるいはエビオスがビオフェルミンをミミかき一杯分、水に溶かしてスポイトでゆっくり飲ませる。
5. くしゃみ
家庭用のネブライザーで5分間ぐらい、直接鳥にあてないよう少量吸わせる。
6. 羽をよくつつく
暗い部屋に入れてやる。
7. 出血している
小鳥は特に出血に対して弱く、すぐに止めることが必要です。もし羽から出血していれば、その羽を抜いてしまい、乾いた脱脂綿をかるくあてがいます。もし爪からの出血であれば、脱脂綿で押さえてから、綿香で焼くこともできます。もし皮膚からの出血であれば、タオル等でくるみ一刻も早く獣医師の所へ行かせます。
8. 目の損傷
鳥が自分で目を傷けないようにまず、湿った脱脂綿で静かに拭いて、非常に少量の人間の目薬をつけてやる。
飼主がしてはいけないこと素人療法
小鳥の治療には古くから伝わる素人療法がありますが、それらの方法が生きるチャンスを少なくしていることも多く見うけられます。以下に述べる事柄については、飼主に絶対に行わないよう指導する必要があります。
1. 病鳥にアルコール類を与えること
ウイスキーやブランデーを数滴うすめて飲ませても鳥は元気になりません。それどころか殺すことになるでしょう。
2. 下剤を鳥に与えること
ひまし油等の下剤は、獣医師の指示があるまでは、決して与えないこと。
3. ペットショップや小鳥屋などから渡された薬品または、人間用の薬品を鳥に投与すること
それらの薬品も、獣医師の指示があるまで決して与えないこと。特に小鳥においては、病状が進むのが早いから、病態にあてはまる薬品と、有効な薬用量を与えることが必要です。多量の薬用量では鳥を殺すことになり、少量の薬用量ではなんの効果も得られません。
4. 鳥の羽などに油類を塗ること
鳥の羽は暖かさを保つための役割をしているので油性物質などを使用すると、体温が保てなくなります。炎症を防ぐためにワセリンなどは決して使用してはなりません。
飼主が患鳥を連れてきたら、次の質問に答えてもらい、それを記録しておく。
- 鳥の年齢(もしわからなければ、飼い始めた期間は?)、性別(もしわかれば)、種類、名前は?
- 鳥はどこから手に入れ、いつから飼育しているか?
- 主な鳥の病状は何か? その病状はいつから始まったか? 何回起こったか?
- 一緒に飼っている仲間の鳥はいるか?
- その仲間の鳥は何か変化があったか?
- 鳥に与えている食物を例記してください。
- 砂、紙、植物など別な食物をよく食べたがるか?
- 食欲は正常か異常か? それはいつからか?
- 活動性は正常か異常か? それはいつからか?
- 日光に当てる(日照時間)時間はあるか? それは窓ごしの日光か?
- 水をよく飲むか? 1日どのくらい飲むか? それはいつからか?
- 最近飼料や飼育環境の変化があったか?
- 排泄物は正常か異常か? 硬いか? 軟らかいか? 水様か? 色は? 数量は?
- 嘔吐はあるか? あれば食物か? 粘液か? 色は?
- 以前に病気したことがあるか?
- 最近または過去になにか投薬をしたことがあるか? その薬はなにか?
- 手のりか? 人間によく馴れているか? よく鳥にさわるか?
- あなたが思う病気の原因はなにか?
- 栄養補給に何かを与えていますか?
- 他になにかペットを飼育していないか?
- 呼吸は正常か? 異常か? それはいつからか?
- 換羽した時期はいつか?
- 繁殖に関してどのような経過があるか?
- 籠から出して運動させるか? それはどのくらいの時間か? その回数は?
患鳥を籠から取り出す前に観察しておくこと
- 診察する部屋のすべての窓やドアが閉めてあるかを確認する。
- 静かな環境で鳥にとって安全な場所かをも確かめる。
- 鳥が羽を立て、目を閉じ、頭を毛の中に入れて丸くなって、ひどく弱っているかを確かめる。
- 少しでも弱っていたら、すぐさま保温のための処置をする。
- 籠の中に吐き出す傾向を助長するもの、例えば玩具や鏡があるかを調べる。
- 籠の形、大きさ、使われている塗料のぐあいを調べる。
- 各餌の品質および餌入れの配置などが適切かを調べる。
- 止り木の直径が同じか、太さが同じかその配置は適切か、またダニなどが付着してはいないかを調べる。
- 籠の底のスノコはあるか、敷紙は何を使用しているか、いつ取り換えたか、羽や吐き出し物があるかを調べる。
- 塩土、ボレー粉、イカの甲(やわらかい側を向ける)の配置と使用の仕方を調べる。
- 鳥のその他の主な症状と、排泄物の数、色、形などを注意深く調べる。
解剖と生理
外皮と体温調節
鳥では汗腺がないので、体温調節作用は呼吸と皮膚がうけもっている。鳥は高い代謝率と体温調節機能を有している。羽毛は、高い体温(40.5~44.5℃)を保つのに、効果的な断熱材として働き、下羽は生体を温める空気を保ち、外羽は冷たい外気からの通風を防ぐ。羽毛は多くの鳥では薄い油層で覆われ、少数の鳥が細かい粉で覆われている。若鳥のような、巣内の鳥は成鳥よりも低い体温で、その羽毛が完全になると成鳥の体温となる。
環境温度が耐えられる限界を超えると、鳥は頸をのばして、大きく口を開き、あえぐように開口呼吸し、羽を伸ばして自己の体温の低下をはかる。逆に体温喪失を防ごうとするときは、羽毛の温熱絶縁作用を利用して、羽毛と羽毛の間に空気を入れて保温するので、羽毛を膨らませ、しゃがみこむので全身が膨らんで見え、だんだん丸くなる。
羽はまた、求愛や攻撃の誇示、造巣活動、防水作用にも役立っているが、もっとも重要な役目は飛翔である。羽毛は消耗するので、時々新しくなるが、換羽は繁殖期終了後に起こることが多い。嘴は常に発育を続け、摂餌、よじのぼり、羽毛の手入れによってすり減り、ちょうど手の役割をしている。
嘴の大きさや形は、鳥の種類によって異なり、食生活と関係があり、嘴の形を見れば、およそその鳥の餌がわかる。鳥には皮膚腺もほとんどないので、あるのは尾腺またはプリン腺、脂腺と呼ばれるもので、これは防水機能があると思われている。尾突起の挙筋上の位置にあって、この腺からの分泌物が、鳥が嘴で羽を整えるときに羽毛に塗られる。すべての鳥類が尾腺を持っているわけではない。
羽毛の重要点として、羽毛は基部を含めて全部を抜き去ったときは、約5~10週間で生えかわるか、途中から切り取った場合には、正常な生理的換羽期がくるまで生えかわらない。換羽は栄養、年齢、性、季節、環境、光周性などが関係するが、鳥にとっては大きなストレスとなるので、換羽中は食物の蛋白質(新鮮な羽毛は蛋白質から形成される)量を高めるなど、飼料を良くする。換羽中は、移転、寄生虫治療、輸送などの鳥に負担となることはできるだけ避けるべきである。
多くの鳥は年1回換羽するが、セキセイインコなどのオーム目の鳥は、1年中を通じてだらだら換毛するが、ピークは春と初夏である。セキセキインコの若鳥では10~12週齢で換羽し、その過程で頭部にある横の縞がなくなる。一般に羽が全部生えかわるのには5~8週を要する。
骨格
鳥が骨格で特異性を有する重要な事柄は次の通りである。
- 骨格は、筋の付着部、内臓の保護と支持、および無機質代謝の機能を果たしている。
- 骨格の特徴は、その軽さにあり、ほとんどの部分に呼吸気と直接連絡する空気隙があることに由来する。これらの含気骨は、効率良く飛ぶことを可能にする。
- よく発達した鎖骨が存在する。
- 鳥では橈骨より尺骨のほうが大きい。
- 鳥の脚では、足根骨がはっきりした形では存在せず、脛骨と近位足根骨が癒合して、脛足根骨を形成し、腓骨は非常に退化している。
- 筋の特微は、飛翔するために胸筋が大きく、脚の内転筋は非常に虚弱なことで、これが脚の障害をこうむるための素因となっている。
- 飛翔するために、鳥は鳥啄突起が大きく発達している。
呼吸器系
- 鳥は、飛翔するために気嚢を有し、気嚢は薄い壁からなり血管は欠如している。気嚢は互いに接触しているが、連絡はない。気嚢は気道を通して空気の流れを受け入れたり、流出したりする「ふいご」として機能している。
- 肺は小さくて緻密で、胸郭の脊壁に堅く固定されているので、肺は位置的変化をしない。
- 横隔膜は、痕跡的であり、機能的な役割はほとんど演じていない。
- 鳥は喉頭蓋、声帯、甲状軟骨が欠如しており、鳴管が存在している。
- 肺中を流れる血管は空気の流れと正反対で、血液と呼吸気とが逆流機能を形成している。これが酸素を効率に利用している鍵となり、高い空を飛べる能力を鳥に与えている。
消化器系
- 鳥には歯がないので、多くの鳥は食物や水をそ嚢に入れる。どちらかといえば、筋胃が食物をすりつぶし、歯の役割を果している。
- そ嚢が存在しており、伸縮可能な器官で、摂取した食物がここに貯蔵され消化をまつ。小さい燕雀目(スズメ目)の鳥ではそ嚢はあまり発達していない。貯蔵以外に、成長して子を養育する鳥では、そ嚢ミルクと呼ぶ栄養分を産出して、雄雌ともこのミルクを逆流吐出して、子に与える。
- 食物が腸に達する前に2つの胃を通過する。その一つは長くて薄い壁の腺性部で、真の胃にあたる腺胃または前胃と呼ばれ、消化腺から、塩酸と消化酵素が分泌される。他の1つは円くて厚壁の筋肉性部で筋胃または砂嚢と呼ばれ、グリットと称される消化を補助する小さな石が入っていて、食物の粒を砕くのを助けている。
- 盲腸は通常一対あるが、セキセイインコなどでは欠如していて、小腸と大腸の間の境界がない。
- 総排出腔(クロアカ)は、尿管と生殖器管を受け入れ、B細胞を産生するリンパ様器官である総排出腔嚢(ファブリキウス嚢)はその背壁に開口している。
- 唾液には酵素が含まれておらず、そ嚢内容物に水分を供給する。
- 鳥では比較的肝臓は小さく、結合組織もほとんどない。胆嚢はセキセイインコでは欠如している。
泌尿生殖器系
- 鳥の腎臓は、後腎型で多数の小さな糸球体をもち、長方形でいくつかの葉に分かれ、皮質や髄質はない。
- 膀胱は、大部分の鳥で欠如していて、尿管は雄では精管の内側、雌では卵管の背側で総排出腔に入る。
- 尿管はぜん動運動によって、尿の通過を助け、正常では尿と糞便が、総排出腔から同時に排泄される。尿酸は鳥の蛋白代謝の最終産物であり、腎小管の機能によって排出される。
- 鳥の腎への血液供給はユニークで、血液は腸と脚から直接、腎に送られる。これを肝門脈系に対して腎門脈系と呼ぶ。ゆえに臨床的には、脚の褥創、腸炎などでは、毒素が血液により腎に運ばれれば腎障害をひきおこす。これが鳥には脚の筋肉注射が向かない理由でもある。
- 多くの鳥では、卵巣と卵管は左側のみが発達している。排卵周期にしたがって、雌は交尾に関係なく卵を産むが、このような卵は孵化しない。
身体一般検査法
病気のある鳥は、軽度のストレスが加わった場合でも、急激に悪化したり、死を招いたりすることがあるので、診察をする前に飼主にそのことを告げておくとよい。
その理由は、鳥の防御機能からであり、実際にはエネルギーを大量に消耗していながらも、見かけ上、健康をよそおう場合があり、診察時のストレスのため、貯蔵エネルギーを使い果たしてしまうと、鳥の健康状態は急激に悪化する。
鳥を籠から出すには、鳥にそっと近づき、手をゆっくりと鳥に近づけ、両翼を体に押さえて身動きできないようにして、鳥の頭を母指と示指の間にはさむか、鳥の頭を示指と中指の間にはさんで小指で押さえ、卵を持つ感じでやさしく保持する。飼主が鳥に馴れていれば、よりストレスを少なくするため、飼主に鳥を出してもらい、飼主の指から鳥を渡してもらうこともできる。また別の方法として部屋を暗くして、鳥をつかまえればやさしく捕えることができる。
カナリアや文鳥などの鳥の場合は、さらに取扱いに注意しなければならない。この種の鳥は、健康な鳥の場合でも、心臓レーシング症候群をおこし、つかまえた直後20~30秒で死んでしまうこともある。多くの場合1~2分後に回復するが、俗に「死んだまねをする」と言われている。この症候群は突然の驚きによって、心拍数が正常を超えることによって血液が心房室を満たすことができず、拍出量が極端に減少し、脳に血液がいかなくなり、鳥は虚脱し、1分以内に死亡する。これは肥満しているセキセイインコに特に見られると言われている。
大型のインコなどの保定には、手袋やタオルを使用し、十分防護できるようにする。いずれにせよ、鳥の保定する場合にはできるだけストレスを避けることが重要である。
また、手の保定の際は、胸部を決して指で押えないことで、鳥の呼吸は、胸骨の上下運動で営まれているからで、窒息の危検があるからである。検査の途中で危険を感じたら、いつでもやめる勇気を持たなければならない。
普通検査には、拡大鏡、ピンセットなどの小道具が必要である。飼鳥の臨床において身体検査がもっとも重要な検査である。
頭部の検査
検査はまず頭部から始める。その理由は、鳥につつかれないよう当面は、頭部に、関心を集中するためである。頭部の皮膚の傷はないか、触診でわかる骨折はあるか、頭蓋骨の輪郭を調べ、羽毛の状態を調べる。頭周囲の羽毛に粘液の乾燥したのが付着していれば、最近嘔吐したことを示す。
| 耳 | 鳥の耳は耳翼が無く目の下やや後方にある。羽をよくわけて、溶出物、閉塞、異物、損傷、寄生虫などの有無を詳細に調べる。 |
|---|---|
| 眼 | 眼については眼瞼の腫脹、結膜炎、出血、角膜炎、腫瘍、瞬膜の病変、白内障などを調べる。眼瞼浮腫と結膜炎は、カナリア鶏痘の初期の病変によく見られ、眼窩周囲の膿瘍はオウムでよく見られる。瞳孔反射なども調べることができる。白内障は、文鳥とオカメインコに多くみられ、セキセイインコにもまれに見られる。鳥が神経質であるということであれば、一度盲目ではないかを疑って、注意深く検査をする必要がある。 |
| ろう膜 | セキセイインコの性別の鑑定に役立つ。雄では青で、雌では褐色ないしピンクである。幼若鳥なものはこの色の区別はまだあらわれない。雌鳥の若年期には、ろう膜は暗褐色で、ざらざらの感じで、雄では暗青色を呈し、この青色は肢や趾の皮膚にみえる淡青色と併せて雄の鑑定の助けになる。時にろう膜は肥大し、角化して色の判別ができなくなることもあるが、鳥の健康にそれほど重要な所見ではない。副鼻腔に通じている膿瘍による蝋膜の腫脹に気を付け、排膿しているかを調べる。蜂の巣状を呈する組織の増殖には、鳥疥癬の感染があると思われ、これはあたかも、粉をふりかけたような感じがある。 |
| 鼻孔 | 蟻膜にある穴が鼻孔で、閉塞していないか、滲出物があるか、などを調べる。 |
| 嘴 | 嘴を噛み合わせてみて、変形していないか、また、骨折、伸び過ぎ、歪み、萎縮、腫瘍、鋏状嘴、脆弱性、薄さなどを調べる。同時に下顎骨の成長度の異常も調べる。蜂の巣状を呈するものは鳥疥癬を疑う。あまりに嘴が薄いのや、過剰に弱く、鋏状嘴になっているものは、イカの甲を与えていない鳥によくみられる。セキセイインコの嘴は、1ヶ月間に1.25cmないし1年間に7.5cm伸びる。口角部に潰瘍を起こす肉芽組織や、ポリープができていないかをよく調べる。 |
| 口 | 口内炎や増殖物、異物、腫瘍などの有無を調べるため、ピンセットや安全ピンを使ってよく検査する。 |
| 舌 | 衣類や夜暗くするための毛布などのほぐれたナイロン糸や繊維などが、舌の根元に絡まり損傷を起こしていないか、腐蝕物質、鋭い物質、熱いものを食べての火傷などを起こしていないかを注意深く検査する。 |
頸部の検査
そ嚢触診により、鳥が食べているかを判定できる。内容物の有無、筋の拡張度や緊張度や壁内の悪臭を伴う新生物の塊などを検査する。鈍性の管を咽喉からそ嚢の方へ入れると、閉塞や詰まりが判り、吸引してその内容物を検査することもできる。セキセイインコにおけるそ嚢閉塞の一般的な原因は、ヨード欠乏による甲状腺異形成である。
胴の検査
1. 胸部
指先での触診で、形態異常などがわかるが、まず第一に胸筋を触診し、アルコール綿でよく毛を分けて、その鳥の栄養状態を検査することが重要である。胸部にはもっとも脂肪が付きやすく、腹部下側にも脂肪が付いているセキセイインコはよく見られる。胸部はまた、異常な組織形成がよく見られ、黄色腫と脂肪腫が最も多い。
聴診器を使用して心音を聴くこともできるが、小型の鳥であれば保定しながら、直接鳥を耳に当てて聴くこともできる。この際、鳥につつかれないようにしなければならない。この方法は体温も感じ取れるのが利点である。正常の心拍数は1分間に300~500と幅があるので、多くの場合心拍数は有意とならない。
鳥の聴診で得られる有用なことは、心雑音または不整脈であり、老齢鳥ではよくみられるもので、運動耐過能力または飛翔能力の低下を示す。徐脈の場合は、通常循環器系の衰弱が相当差し迫っていることを示す。
呼吸器障害は、普通容易に判定できる。呼吸に雑音があれば、どういう雑音かを調べる。もっともよい方法は、マイクロホンによる聴診であるが、静かな所で耳を傾けてもかなり知見が得られる。
a. 頭部の歯擦音またはヒューヒュー音…鼻道の乾燥性の部分的障害で、乾燥性溶出物が外部より観察される。
b. 頸部と頭部の舌打ち音…ほとんど完全な上部気道閉塞か、可動性の滲出物充満。
c. あわだち音、喘鳴音、ガラガラ音が気管で聴こえる…声門部と気管の閉塞性病変
d. 間欠的な咳とくしゃみ、この前後にゴクリと飲むような動作…トリコモナス症、カンジダ、開嘴虫(気管虫)感染、刺激性ガスの吸引、喉頭や気管の異物。
e. 発声本能、声の高低の変化……甲状腺肥大、腫瘍、心拡大などの気管下部や鳴管の圧迫。ちょっとしたストレスで死を招く。正常な呼吸数は1分間に85である。気嚢は11ヵ所あり、頸部、腋窩部、前胸部、腹部に各2ヵ所で、鎖骨部に1ヵ所ある。気嚢に慣性伝染病が起こると、ときどき「ちゅうちゅう」という音が聴かれる。気嚢が破裂すると、皮下に空気が留ることがある。
2. 腹部
触診は示指で行うのが最良である。過脂肪でない鳥は、肝臓の辺縁と筋胃が認められる。通常、腹部臓器は柔らかい弾力性のある感じで触知できる。
卵停滞の場合は、硬い卵型塊を総排出腔のあたりに触知できる。腹腔内の病的変化を見つける鍵となる重要な点は、剣状突起と恥骨との幅であって、通常5~7mmぐらいで、それよりも間隔が長いと、腹部隆起があるともいえる。またこの間隔は、雌雄の判定に使われることもある。
3. 後部
尾根部を触診して、尾腺に腫瘍性増殖があるかを調べる。老齢鳥はその傾向が強い。増殖物は、扁平細胞癌、類表皮嚢胞、平滑筋肉腫、黄色腫などが普通認められる。尾腺はときに、腺が詰まり、尾腺炎を起こす。
肛門部に便または尿酸塩が付着していれば、消化器障害の確証となる。肛門部周囲の皮膚の肥厚は鳥疥癬の感染を示唆する。
尾羽が折れていれば、出血することがあるから、見つけたら引き抜いておく。
翼の検査
注意深く翼を拡げ、裂けていないかなどを診る。
皮下に増殖物がないか調べる。通常これは関節部によく見られ、文鳥などによく見られる。関節部をよく調べ、痛風を伴う石灰様物質の沈着の有無を調べる。翼はどの方向にも動くので、単なる打撲を骨折とあやまらないよう注意する。
脚の検査
止り木を鳥が脚で掴みしっかりと立っているかを調べ、注意深く骨折の検査をする。また脚の強さ、掴みぐあいを調べ、左右とも同じかを確かめる。片脚の異常は、腹腔内腫瘍や動脈血栓が血流の阻害をするために起こることが老齢鳥において認められている。
温度変化を診るために、人間の手よりも唇で悪い脚を触れて、次いで正常な脚を触れて、多少とも温度に変化があるかを調べる。また脚の筋群の腫脹にも注意する。
趾では、瓜の伸び過ぎに注意する。細い糸などが巻き付いて血流を妨げていることがあるので注意する。
皮膚および羽の検査
ダニ、シラミ、腫瘍、羽の変形、すりきれ、脱毛などの有無を調べる。また羽毛の光沢、正常な生理的換羽を行っているか、フレンチモルトがないか、自分の羽をついばんでいないかを調べる。
体重の検査
鳥における体重の測定の重要性は、いくら強調してもしつくせない感がある。通常、鳥をビニールの袋に入れて、封筒用の秤(発売元:王様のアイデア)を使用するか、翔べない鳥に対しては家庭用料理秤で測る。
大型の鳥に対しては十分安定した止り木を、丁字型に作りその下に土台を作る。測定は止り木ごと行い、後で止り木の重さを引けばよい。
セキセイインコの標準体重は30~35gであり、文鳥は20~25gである。体重はまた、正確な薬用量を求めるためにも欠かせないものである。入院中や加療中のすべての鳥は、治療指針のために毎日体重を測定する。患鳥の体重の変化は、予後の判定に重要となる。
糞便検査
鳥が新しい環境にきたために、また診察の後に水様の下痢様便をいくつか出すことがあるが、これは興奮のための神経性下痢であるので、まちがわないようにしなければならない。健康なセキセイインコの糞便は硬く、2つの部分からできている。すなわち1つは、白い尿酸塩(尿酸)で、他は暗い色の糞便物質である。正常な糞は、”の”字型で、”仔牛の眼”と表現されるように、暗褐色の便が中心に位置し、半固形の白い尿酸塩を取り囲む。
便の数は、平均して25~50個であり、正常な糞は完全な固体であって、原形をいつまでも保持し、周囲に汚れを与えない。糞の周囲に非常に小さい班点があるのは正常であり、特に鳥が野菜や果実を食べた時に、このような班点が出やすい。鳥が健康であれば、臭気はない。
糞の数が少ないときは、食欲不振を示唆する。糞の内容の半分以上が尿酸であれば、腎疾患を疑うか、または蛋白質に富んだ食物の摂取、または消耗性疾患によって、蛋白質の異化が亢進した結果、尿酸の排出が増加したためと考えられる。下痢と多尿や多量の尿の排出と混合してはならない。
よく緑便と言う言葉が使われるが、これはなにも特定な疾患を表わしているのではなく、セキセイインコなどの胆嚢を持たない鳥は、食物の摂取の低下と共に糞の緑色が強くなり暗色が増す。
その理由は、胆汁が食物の量とは関係なしに排出されるので、1日も食物を取らないと便は緑色になるのである。緑便は胆汁を貯える胆嚢を欠如している鳥全部に起こる。しかしながら、この所見の意義は不明である。
便中に組織片や血液があれば、重篤な炎症があり、通常感染症が小腸または大腸にあることを示唆する。種子類が不消化のまま出てくるのは、消化管の運動過剰または筋胃壁の萎縮を示す。消化器系に何らかの異常があれば、グリットは排出されてしまうと考えられる。このため種子類の消化が不良となる。このような場合には、少しずつグリットを補給してやればよい。
鳥の糞の検査は診察の重要な部分で、通常それを行うには、あらかじめ温めたスライドグラスとカバーグラスを使用して、なるべく新鮮糞を使用し、温めた生食を加えて、できるなら位相差顕微鏡で検鏡する。
飼鳥に重要な疾患である、ジアルジア、コクシジウムなどの寄生虫が見つけられる。さらに潜血反応をみたり、デンプン反応(ルゴール反応)を調べると、より対果的である。できれば尿酸塩の部分だけを注射器で吸引して、尿検査用のテストペーパーで調べることも可能である。
その他細菌に対する薬剤決定のため、糞便の培養も行うことができる。下痢の原因としては、寄生虫、感染性(細菌、ウィルス、真菌)、食餌性、肝炎、ストレス、腎疾患、中毒などがあり、飲水過多の原因としては、食塩中毒、ストレス、脂肪過多、卵管炎、尿崩症、糖尿病、腸炎、?嚢炎、腎炎、卵巣嚢腫、腹水症、痛風、下垂体腫瘍、コルチコステロイド過剰投与時、肝炎、卵管水腫、卵性腫膜炎などが考えられる。
その他の診断的手法
| 体温 | 体温を測るには、電子体温計を肛門より挿入し、左側の卵管まで入れる。鳥では体温が非常に幅があることや、測るときのストレスを考えて日常の診察には大型鳥以外これを行わない。しかしながら、鳥の麻酔時などのモニターなどには有効な手段である。一般に、鳥の体温は低体温の場合のみ有意である。 |
|---|---|
| 血液検査 | セキセイインコや文鳥などは、採血時やその後のストレスなど考えて日常の診察にはすべてはこれを行えない。特に衰弱している鳥には禁忌である。 100g以上の鳥だと通常は、あまり困難がなく行える。 爪または翼の静脈から採血する。 PCV、TP、BUN、血液塗抹標本などは、比較的簡単に測定できる。その他、WBC、RBC、Hg、尿酸の測定などがよく行なわれるが、血液検査は診断と予後の判定に有意であるので、安全に行うことができると判定した場合には、広くこれを応用すべきである。 |
| 腹腔穿刺 | 腹膜炎、腹水、腫瘍などの診断に有用である。が、腹部気嚢を損傷しないよう行う。 |
| 鼻孔 | 生前および死亡後における病変の細胞学的検査によれば、驚くほどの多くの診断的知見が得られる。溶出物などの病変部の塗抹の作成と判定は、簡単に重要なデータを得ることができる。 |
X線検査法
X線撮影は、内部疾患が疑われ、元気消失などの非特異的症状の病歴で来院する、飼鳥の大多数に適用されるべき診断方法である。X線検査は侵されている器官に関する情報としては病理学的診断とともに有用であり、しかも生前の情報が得られることに価値がある。
しばしば傷害性か感染性かが明らかとなり、診断および治療の決定に役立つ。臨床症状が非特異的なほど、X線所見に基づいて診断されることが少なくない。X線検査は、飼鳥の大きさに関係なく、実施できることやすぐに結果がでることなどで、もっとも役に立つ診断方法と思われる。
X線検査が禁忌な場合は、病鳥が保定したりするためのストレスに耐えられないと判断されたときが禁忌となる。そのようなときは、支持療法によって一般状態が改善されるまで撮影を延期することがよくある。米国における鳥病の専門医であるDr. Lafeber, Dr. Altmanらの病院、及びカリフォルニア大学の獣医科病院では、鳥類の臨床において、来院する鳥の50%以上がX線検査を受けている。
適用症
1. 骨格系の病変
骨格に何かの疾患や、傷害が疑われる場合や、その進行度や、病変の広がり方を調べる。 例えば、骨折、脱臼、各種の腫瘍、軟部組織の腫脹などの場合である。
次に給飼の不適切による骨の代謝疾患で、例えば栄養性二次性上皮小体機能亢進症(クル病はほとんど常にこれを合併する)、クル病(成長した動物では骨軟化症といわれる)、骨軟化症などでこれらは俗に、栄養性脚弱症または脚マヒと呼ばれており、骨の濃さが減少し、皮質が肥厚し、しばしば支持骨折(若木骨折)が認められる。そのような代謝疾患や、整形外科的な疾患の経過をみて予後を判定するためにもX線検査は応用されるべきである。
また骨の変化として、汎骨炎(骨の髄腔がまだらに見える)や、大理石骨症(骨化石症とも言い、骨の濃さが増加する)などは、雄の場合は精巣の異常、雌の場合は産卵中か卵巣の異常を示唆しているので診断に有用である。
2. 腹部系の病変
腹部によって起こる疾患はしばしば臓器特異性を示さず、羽を膨らましたり、全身が衰弱したりする程度で、X線撮影は他の情報にない、診断をくだす助けとなる。
例えば、筋胃(通常、その内容物がX線不透過性であるから、容易に識別できる)は、多くの腹部疾患において特異的な変位を起こす。
肝臓腫大は、筋胃を後方へ背側へと押しやり、後腹部の腫瘍塊に対しては、筋胃は前方へ変位する。肝臓の腫大はまた、腹背像にて心臓と肝臓の作り出す形、すなわち砂時計の形の、ウエストの部分の消失をきたす。
また腹部脊側の腫瘍塊(例:腎腫瘍)に対しては、筋胃を腹側へと変位させる。
その他、腹膜炎に起因する遊離腹水(腹部後方が拡大し、ときに筋胃と腸が前方に)や気嚢炎などに見られる、気嚢の濃度がいろいろな程度に増加する疾患、心臓の拡大、腹水(スリガラス様所見)、卵塞(卵の数と位置及び軟卵の程度が判定される)、消化管内の異物、性腺が腎腫瘍または嚢胞(骨盤部背方の濃度が増加し、筋胃と腸の腹側変位、遊離の腹水が在存することもある)、卵巣の膿腫や腫瘍および卵管の蓄膿や水腫(後腹部の濃度が増し、筋胃が前方に変位し、骨の変化が発現し、卵管内にしばしばカルシウム沈着が認められる)などの確認も、X線写真によって行うことができる。
3. 呼吸器系の疾患
鳥はその特性から呼吸が早いので、X線撮影するにあたっては少し不利であるが、X線撮影の最高の技術とは、鳥に最小のストレスで、撮影を行うことである。
鳥には気嚢があるので、うまくコントラストがつく。呼吸因難は最もよくみられる臨床症状で、その病因は、身体一般検査だけでは確定できないことが多い。このような時にX線撮影を行えば、病度の部位や病状の性質についても示してくれたり、炎症や腫瘍、また外傷性の病因の手助けとなる。
例えば、呼吸困難が次のような疾患についても、X線は診断の有用な手段となる。すなわち肺炎(細気管支の壁が肥厚して、透過性が低下し、”蜂巣構造”は完全に消失する)、気管虚脱、肺出血(肺内の濃度が部分的に増加)内臓痛風(心臓、肝臓、腎、心臓、気嚢などにおいて部分的に濃度が増加する)、気嚢炎、口腔内の異物、腹部の腫瘤塊病変や腹水などによる気嚢や肺の圧迫などである。
正常X線解剖学
鳥には横隔膜がないので、胞腔と腹腔が連続している。肺は胸腔の背部に位置しこれを側方から撮影すると、蜂巣状構造にみえて、もっとも評価しやすい。
腹一背方向の照射においては、細気管支は横断する判然としない線状構造にみえる。腹一背方向の撮影は細気管支がよくみえないが、肺疾患の側面を知ることができるので必要である。
気嚢は胸部および腹部の透明域として判別でき、腹一背方向の照射では、腹部気嚢が腹部後方の内臓の側方にみられる。右腹部気嚢は左のそれよりいくらか後方に広がっており、両側とも総排泄腔の横で終わる。気嚢の壁は判別できないのが普通で、鎖骨気嚢は腹一背方向の撮影では、肩、関節部分にさまざまな形で認められる。側方から撮影すると、胸部気嚢は肺の腹側に透明域として判別される。
そ嚢は胸郭の入口に位置して、摂取した餌で膨らんでいるのが普通である。そ嚢の大きさは種によって異なり、また種によっては欠如している。
前胃は食道と筋胃の間に位置する消化管のまっすぐな管状部分である。前胃は、猛食類および海鳥の一部において貯臓器官の役割を果している。したがって、内容物の量に応じて大きさはきわめてさまざまである。前胃は側方からの照射で、胸腔尾側と腹腔前部で胃に向かって横行している。ときに、前胃のなかに放射線を透過しない砂がある。
筋胃は可動性であり、腹腔内に容積を占める病巣があると位置がずれる。
腸は腹部尾方を占めている。総排泄腔はときに空気が充満した円形構造にみえる。
腹部中央および後方の背部は腎、副腎および性腺が占めている。腎の前端は骨盤骨から腹方に突出しているので判別できるが、腎の主体は骨盤骨に埋没していて、X線でははっきり識別できない。
脾は小さくて円形で、軟部組織の密度を示し、腹部中央で側方から撮影すると、胃の背側かつ前胃背部に重なって認められる。腹一背方向の撮影では、はなはだしく腫大していない限り、脾を判別できない。脾はオウム病が疑われる症例において判別すべき重要な器官である。
鳥類の正常X線解剖図を、Dr. J. P. Morgan, Dr. Sam, Silverman 著者の「Techniques of Veterinary Radiography」の第3版(1982年)より引用したのが下記の図である。
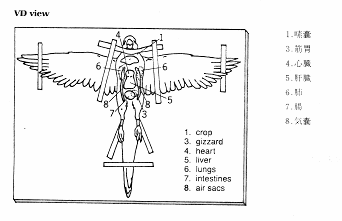
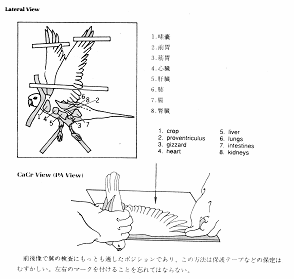
撮影方法
我々は普通セキセイインコなどの小型な鳥には、42KV、0.03秒、300AM、FFD(焦点距離)100cmのブレンデなしで、撮影しているが、実験的に多くのX線撮影をして、各自が一番よい条件を見つけだすのがよい。
鳥のX線撮影においては、きわめてわずかな撮影条件の変動でX線像が大きく変化することがある。そこでアルミニウムなどの板を、管球の下に置いて撮影すると、比較的安定したX線像が得られることがある。FFDを短くして、X線照射装置の能力の不足を補うこともできる。露出時間はできるだけ短ければ、ブレの無いよいX線像が得られる。より鮮明なX線像を得ようとすれば、ノンスクリーンフィルムを使用したり、人間の乳房撮影用のフィルム等を使用することがよいが、これらは概して高価である。
保定
オカメインコより小さい鳥は鎮静させなくても、ほとんどの検査が可能である。もっと大きい鳥あるいは扱いにくいオウムは、塩酸ケタミン0.05mg/kgを筋注して鎮静させることができる。この投与量では有害作用はみられず、鳥は45分以内に歩きまわるようになるのが通例である。
保護テープはキープシルク(ニチバン)が通気性もあり、皮膚および羽毛を傷つけることが少なく、はがすのが容易なので好ましい。大部分の検査は、翼の遠位部、跗蹠骨の部分および前頸部にテープを貼って行う。鎮静させなかった場合には、さらにテープを貼る。テープは呼吸運動を妨げないように貼るべきで、鳥の呼吸には胸壁および腹壁の自由運動が必要である。
側方からの撮影は、鳥を側臥させ、両翼および両肢を身体から離して行う。下になっている翼および肢は対側のそれより前方におく。下になっている側、および前方に位置する翼ならびに肢には、適当な右あるいは左を示すマークをつける。翼および肢を十分に伸ばせば、腹部および胸部臓器に重なることはない。
腹一背方向の照射は、両翼および両肢を十分かつ対称的に伸ばして行えば、もっとも多くの情報が得られる。胸骨を脊椎と平行におけば、身体の回転はほとんど起こらない。
検査の前、検査中および後に支持療法を行えば、X線検査に伴うストレスを最小限にとどめることが可能である。検査中は、熱電球を鳥に当てておくとよい。検査が終わったら、温度、湿度および酸素濃度を調節してある保育器に鳥を入れる。
消化管の造影検査
消化管内に変位する疾患や、消化管以外に起因する疾患、例えば腹部膨満に対して診断できる強力な手段となりうる。セキセイインコなどには、温めた100%硫酸バリウムを0.5~0.7ml、そ嚢にゆっくりチュ一ブで投与し、2時間後に2方向撮影する。目的によって、造影剤注入直後や、5~10分後、その後30分間隔で撮影することもある。
治療の原則
一般に体力のない鳥類の治療の原則は、強力な支持療法(非特異的な療法)から、個々の異常病変に対して行う特異的な療法へと進む場合が多い。それだけに、早期発見、早期治療が必要である。いずれにせよ、衰弱した鳥に対しては、共通した行うべき事柄が多くある。治療の最高な方法は、最小のストレスで治療を行うことである。不必要なストレスは絶対に烏にとって禁忌である。鳥を診察するものは、だれでも検査中や治療中に、手の中で死亡することにまま出会うが、できるだけ末然に防ごうとする態度が必要である。
衰弱した鳥の最初に行うべき処置
1. 熱療法
通常、保育器に入れて、温度29~32℃、湿度70%以上、酸素20~30%などを目安にセットする。保育器がなければ、コンテスト籠に、通気孔を作ったビニール袋を入れて、酸素を引き入れ、籠の下にヒーターを入れるなどして暖かさを保ち、保温できる静かな環境の部屋に置く。
また経済的な方法として、アルミホイルを用いて筒を作り、小型の鳥などはその中に入れてしまい、酸素の排気口と入口を前後に作って、上から熱電球などで保温する。鳥は暗い環境下に置かれ、すぐ温まりやすく、酸素も少量で、簡単な道具でできるのが利点である。しかしながら鳥は暗いと、食物を取ることができないので、常にこのことに注意すべきである。
2. 給餌療法
飢餓状態にある鳥や、食欲不振のある鳥は、チューブにて強制給餌をさせることができる。非常に衰弱している鳥は熱療法のころあいを見計らって、チユーブやスポイトにて初めに5%ブドウ糖を30分間隔で3回与える。
症状の改善が認められたら、次に低アレルギー性大豆型食品で、幼児用ミルク代用品である「ボンラクト」(和光堂、薬局製剤)を投与する。このミルク代用品が最適で、ベビーフードではカロリーが不足し、ミルクやクリームでは乳糖が多すぎ、アミノ酸製剤では下痢を起こす。卵の白身の投与は禁忌であり、ブドウ糖の10%以上のものは脱水を起こす可能性があるので投与しない。
とにかく重要なことは、インコやカナリアは2日間食べないと死ぬということである。液体→流動食→固形食とよくなるに従って変えていく。鳥には好みの食物があるので、食欲不振のときなどはそれらを補ってやるが、食べるからと言って人間が食べる刺激物(例えばコーヒー、コーラ等)は絶対に投与しない。
重要なことは、そ嚢が空になるまで与えないことで、与えればそ嚢の酸敗をおこす。これは食物が長くつまっていると、発酵するからである。そ嚢はいつでも注意深く触診し、酸敗などの異常が認められたら、それを取り除き、通過をよくするため、ミネラルオイル(流動パラフィン)などでマッサージをしたり、抗生物質などで処置した後、あらためて液体や流動物などから投与を始めなおす。
3. その他の重要な看護法
a. すきま風が入らないようにする。
b. 低い止り木にする。
c. 水と食物を食べやすい位置に変えること。
d. 暖かくした水に5~10%のブドウ糖を入れてやること。
e. 鳥に十分休息をとらせること。
f. 暗い部屋において体力の消費を防ぐ。
g. 1日1~2回各1時間ぐらいネブライズすること。
h. 皮膚や羽毛が食餌で汚れたときは、羽の絶縁効果が失われるので、これを防ぐために暖かい湿った布できれいに拭いてやる。
i. 元気な仲間の鳥の声が聞こえるようにしてやること。
飼鳥の投薬法
薬物を投与するときのストレスで、衰弱している鳥を死に追いやることがあるが、多分その鳥は投与しなければ死ぬだろうから、できるだけやさしく、ストレスのないよう投与をしなければならない。飼鳥の場合は、投与したときの薬効や薬用量、血中濃度などに関しては、ほとんど経験的なもので、あまり研究が行われてないといってよい。
1. 飲水に混ぜての投与
多数の鳥に対して、鳥をつかまえなくても投与できたり、用意が簡単であるが、鳥はその水を飲まなかったり、飲水量がはっきりしなかったり、飲んでいるかを調べる必要がある。大型鳥への投薬や、予防的健康管理薬の投与に対しては、よい方法と思われる。
2. 滴下投与
飲水中の投与より一歩進んだ方法であるが、飲み込むことを拒絶する鳥や(薬剤が無駄になる)、速く投与すると誤嚥性肺炎になったりすることもあるので、多くの場合、鳥をつかまえる必要がある。しかし投与が簡単で、注射法ほど正確な薬用量を必要とせず、消化器系の感染などに適する投与法である。プラスチック製のスポイトなどを用い、ガラス製のものは用いない。
3. チューブ(挿管)投与
もっともよく用いられる投与法で、翼状針のポリエチレンチューブの部分を用いたり、16ゲ一ジぐらいの大きさの、3~4cmの長さの針の先端を切って鈍にして用いたりする。大型鳥においては、比較的太いチューブを使用しないと気管に入ることがあり、一度吸引することや、触診でよく確かめることなどが、必要である。その鳥の投与量を超えない量で投与する。
- セキセイインコ 1ml
- カナリア 0.25ml
- 文鳥 0.1~0.5ml
- オカメインコ 2~4ml
- 中型オウム 10~15ml
- 大型オウム 20ml
4. 薬剤貼付食
まとめて多数の鳥に投与でき、つかまえたりのストレスがないが、摂取した薬剤量を決められないし、食べるかどうか調べたり、薬剤が貼付された殻が無駄になったりする。しかしながら、予防的健康管理薬などの投与にはとても便利な方法である。最も多く使用される薬剤は、エビオス末:ビオフェルミン末:カルシウム末(BPDかデーカル)を6:3:1ぐらいの割合で混和し、それをカラ付やむき出の入った餌入れに入れて、よく混和して常時それを投与します。余った薬は瓶の下の方にたまります。
餌の管理で重要なことは、その餌を使い終わるまで、その保存用の餌入れに新たな餌を入れないことで、使い終わらないうちに入れるといつも下の方は古い餌が残ってしまうので、変質してくるからです。もちろん虫などの発生に注意します。
また別の薬剤貼付剤として重要なものに、オウム病を人間から守るためのものであって、米国では輸入される鳥には、少なくとも45日間テトラサイクリンの投与が行われているが、我が国においては、毎年約300万羽の鳥が輸入されているが、ほとんどフリーパスの状態で輸入されている。米国ではテトラサイクリン入りのキビが発売されているが我が国にはない。そこでわが国では家庭でオウム病の予防を行う必要がある。
その方法は、小児用レダマイシン、ドライシロップ(武田薬品)、1包(1g中テトラサイクリン60mg含有)に対しエビオス末5gをよく混和して、それを皮付き餌120gとよく混和して同じように45日間以上投与するとよい。また水30mlに対して1/2包(30mg)を溶かして同じように与えることができる。
5. 筋肉注射法
筋肉注射はもっとも確実な方法で、薬剤が投与され、好んで行われる方法である。注射部位は胸筋に行われ、正確な投与量を決めるため体重を測る必要がある。注射器はマイクロリッター注射器がベストであろうが、高価な点や壊れやすいので、通常我々は我が国で入手できる最小単位の1ml用デスポーサブル注射器を使用している。
お推めできるものには、モノジェクトの結核用1.00cc用のもので、これは0.01ccの目盛から成り、0.1ccずつ10の単位に分かれている。またテルモのインシュリン用1ml/40単位のものでもよく、これは目盛が0.025mlから成っている。いずれの注射器も、針は変える必要がある。テルモ26G1/2、0.45×13㎜、SBのものが最適で、これは針先がショートカットとなっており、他の25~26Gのものは針先の点で難点がある。
針はできるだけ常に新しいものに変えることが必要で、鈍となったものは鳥に損傷を与えることがある。注射するにあたっては、あらかじめアル綿にて毛を分けて部位をよく確かめて、確実に筋肉に投与する。あまり深く刺すと危険である。注射部位から失血がないかをよく確かめ、綿で10秒間ぐらい押える。注射は死んだ鳥などに、墨汁注射を行って筋肉のどの部位に注入されたかなどを調べるかして、あらかじめよく練習しておくとよい。
6. 皮下注射法
鳥が衰弱して水を飲めないときや、外科手術の前に水分供給をはかるために用いられる。普通、腋窩部分に5%ブドウ糖、乳酸リンゲルなどを投与するが、頸部皮膚、鼠径部にもできる。皮膚は弾力がないから、注入しても押し戻されてしまうことがある。セキセイインコなどでは両腋窩部に0.4mlぐらいずつ入れることができる。
7. 洞内注射法(副鼻腔内注射法)
眼窩の下の洞内に注入して洗浄するために用いられ、慣性洞炎などのときに、ときどき行なわれる方法で、生食でうすめた抗生物質などを投与する。
鳥の頭をしっかりと固定し、アル綿で口角の部分をきれいに拭いてやると、穿刺部位である羽毛のない三角域が現れる。この域の中心の少し上部をボールペンで軽く押すとへこむ部分があり、穿刺部位である。あまり鋭くない針を、洞内に2mm以下の深さで注入する。余分な液体は鼻孔から出てくる。両側から出れば、他側の注入は必要がない。あまり暴れる鳥に対しては危険で、麻酔が必要になってくる場合もある。
8. 鼻腔内注入
軽い洞炎などの場合、鼻孔を閉鎖しないように粘調度の低いものを用いる。ゲンタマイシンの点眼用の液体(1cc、3mg含有)が最適で、特に燕雀目の鳥には使い易く、鼻に1~2滴たらすだけでよい。
9. 眼剤(局所薬)
軟膏は第3眼瞼があるためか、ベトつくので適用しにくい。抗生物質、ステロイド等がほんの少量適用されるが、何回も投与する必要がある。
10. ネブライザー
呼吸器疾患に適用される。空気のもれない所に蒸気を充満させて、その中に鳥を入れておく。普通は保育器にて行うことができるが、温度が高くなりすぎないよう注意する。普通治療は7日間連続して行う。
通常使用される薬剤として、ガンタマイシン(エッセクス日本)40mgのものを5ml、生食15mlに溶媒して、吸入用薬剤アレベール(日本商事)を1滴用いて、45~60分間ぐらい使用する。
その他使用できる薬剤として、カナマイシン、クロラムフェニコール、サルファジメトキシンがあり生食15mlに対し、200mgの量で使用する。
11. その他の投薬法
静脈注射は救急用の手段でセキセイインコの場合、翼上腕静脈に5%ブドウ糖1mlをゆっくり1日2回静注(27G使用)する。より重篤な鳥には、ソルコーテフ(100mg)、0.01mlが加えられる。静脈注射には血腫が起こりやすいので注意する。
腹腔内注射は、気嚢があるため禁忌である。結膜内注射は結膜炎のときにまれに行うことがある。局所薬は通常、エリザベスカラーが必要である。
実施できる薬剤の投与量
これらはみなセキセイインコ(平均体重30~35g)を標準としたもので、日常使用される代表的な製剤を列記する。
1. 治療用内服液薬
| テトラサイクリン | 水20ml中に28mg自由飲水 |
|---|---|
| クロラムフェニコール | 水20ml中に31mg自由飲水 |
| タイロシン | 水20ml中に50mg自由飲水 |
| リンコマイシン | 水20ml中に50mg自由飲水 |
| エリスロマイシン | 水20ml中に50mg自由飲水 |
| カナマイシン | 水20ml中に80mg自由飲水 |
| マイコスタチン 懸濁用シロップ (三共) |
10万単位/mlを体重30g当り約2滴を1日2回。抗真菌剤。 |
| テストステロン (テスチノン、持田製薬) |
10mg/ml、水30ml中に25g当り2滴入れる。カナリアの脱毛に有効で1~4週間与える。またカナリアの脱毛には、内分泌系を刺激するため日照時間を変化させる。例えば始めの2週間は1日8時間暗くし16時間明るくし、次の2週間は逆にする。普通これにて2ヶ月以内によくなる。 |
| デキサメサゾン (日本全薬) |
2mg/ml、2.3ml当り1滴を溶かして自由飲水、または1mlを水3mlに溶かして1日2回1滴を嘴へ滴下する。 |
| フロセマイド (ラシックス、20mg/2ml) |
2倍に薄めて1日2回1滴、嘴へ滴下。腹水、心筋症に有効。 |
| ジゴシンエリキシル (中外製薬0.05mg/ml) |
1日1滴嘴へ滴下。心不全、腹水に有効。 |
| アロプリノール (アロリン、昭和新薬、100mg) |
つぶして10mlの水に溶かし、水30ml中に20滴入れ自由飲水。通風の高尿酸血症の改善。 |
| サルファジメトキシンシロップ(100ml/5g) | 水30ml中に2滴、自由飲水。 |
| メトロニダゾール (フラジール、塩野義) |
250mg、つぶして25mlの水に溶かし、体重10gにつき1滴、1日1回5日間嘴へ滴下。フィンチ類に毒性あり。ジアルジアの治療薬。 |
| テラマイシロップ (1ml/25mg) |
1日2回、1回1滴、嘴へ滴下。 |
| リオマイシロップ (1ml/5mg) |
1日1回、1回1滴。 |
| クロマイシロップ (1ml/31.25mg) |
2倍に薄めて1日2回、1回1滴、嘴へ滴下。 |
| レスチオニンC (三鷹製薬、動物用100ml) |
水20ml当り1mlを溶かし、自由飲水。脂肪肝の予防と治療。 |
| ユベラシロップ (エーザイ、動物用) |
原液を1滴、嘴へ滴下。 |
| リナトーン (ランバートケイ、動物用) |
1日3~4滴を、嘴へ滴下。同じく脂肪肝予防治療剤。 |
| チレオイド (三共、50mg) |
水30mlに12錠を溶かし、1日1回3~4滴(約10gに1滴)、嘴へ滴下。または餌450g当り、6~12錠を混入して自由に与える。甲状腺製剤で脱毛症、卵巣機能障害に適用し、通常3~6ヶ月投与する。 |
2. 治療用注射薬
通常我々は、注射薬の場合は量が少なすぎるので、あらかじめ小鳥用のバイアルを別に作り、普通原液をあらかじめ2~9倍に蒸留水にて稀釈しておく。すると、1mlの注射器にても十分使用できる。通常実際の注射量を、最低0.05mlとしている。
| テトラサイクリン (50mg/ml) |
原液を5倍に稀釈して、0.05ml筋注1日1~2回。 |
|---|---|
| ゲンタマイシン (40mg/ml) |
原液を4倍に稀釈して0.05ml筋注、1日1~2回。 |
| タイロシン (50ml/ml) |
原液を3~5倍に稀釈して、0.05ml筋注、1日1~2回。 |
| サルファジメトキシン (100mg/ml) |
原液を7倍に稀釈して、0.05ml筋注、1日1回。 |
| デキサメサゾン (2mg/ml) |
原液を5~7倍に稀釈して、0.05ml~0.1ml筋注、1日1~2回 |
| ドキサプラム (ドプラム、キッセイ薬品、20mg/ml) |
原液を4倍に稀釈して0.05ml静注する。 |
| ケタミン (50mg/ml) |
原液を3倍に稀釈して、0.05~0.12ml筋注する。 |
| アデラビン7号 (三和化学) |
原液を2倍に稀釈して、0.05ml筋注。1日1~2回。 |
| トラネキサム酸 (バソラミン、第一製薬、 動物用、50mg/ml) |
原液を5倍に稀釈して、0.05~0.1 ml筋注する。1日1~2回。 |
| ジェンタマイシン+ テラマイシンの合剤 |
両剤を混合して、その原液を4倍に稀釈して、0.05ml筋注、1日1~2回。 |
| ジェンタマイシン+ タイロシンの合剤 |
両剤を混合して、そして原液を4倍に稀釈して、0.05ml筋注、1日1~2回。 |
| 生食、5%ブドウ糖、 乳酸リンゲル |
原液を0.2~0.3ml皮下注、1日1~2回。 |
| アトロピン (0.5mg/ml) |
原液を10倍に稀釈して、0.03~0.06mlを筋注。 |
| グルコン酸カルシウム (カルチコール、大日本製薬) |
8.5%の原液を10倍に稀釈して、0.1~0.3mlを筋注または皮下。 |
| カルニゲン (日本ヘキスト) |
原液を10倍に稀釈して、0.05ml筋注。1日1~2回。 |
| バリアン (エーザイ) |
鳥に直接塗布する。ワクモ、トリサシダニなどの吸血害虫駆除剤。 |
| アミトラズ (ダニカット、日産化学) |
36ml当り1滴の原液を滴下し、それを綿棒等で鳥に直接塗布する。3~5日間に1回ぐらい使用。鳥の疥癬に有効である。 |
| イソジン | 随時、鳥に直接塗布。 |
3. 外用その他
| バリアン (エーザイ) |
鳥に直接塗布する。ワクモ、トリサシダニなどの吸血害虫駆除剤。 |
|---|---|
| アミトラズ (ダニカット、日産化学) |
36ml当り1滴の原液を滴下し、それを綿棒等で鳥に直接塗布する。3~5日間に1回ぐらい使用。鳥の疥癬に有効である。 |
| イソジン | 随時、鳥に直接塗布。 |
麻酔と外科
麻酔
飼鳥の臨床をより一歩進めるためには、麻酔法に慣れていなければならない。麻酔法は外科技術より重要で、治療や検査を行うためにも必要なときには、恐れずに行えなければならない。
より重要な原則として、麻酔なしでも手術が行えれば、もちろん麻酔は不必要となる。小鳥の特異性で、元来鳥はホ乳類に比べて麻酔に対し抗抵性がないので、できるだけ麻酔は必要最小限に行うことが重要である。
実際の麻酔の重要点
- そ嚢の手術を除いて、絶食はしない。鳥は血糖値が高いので、そのため代謝率が高く、絶食をすれば肝のグリコーゲンや解毒の作用が低下するからである。
- 麻酔中も回復期も鳥を暖かくしてやる。ヒーティングバックパットまたは補助ライト等を使用して、体温の低下を防ぐ。鳥は高体温下のみで正常な代謝力が営まれるので、体温の低下は死を意味する。それゆえ麻酔中は体温をモニターすることが必要である。
- 麻酔はできるだけ軽い麻酔、すなわちナルコ一シスの状態に保つことを心がけるか、これはしばしば困難を伴うことがある。そのため心拍数をモニターしたり、手術の覆い布は透明なものを使用したりして、常に呼吸がその深さを観察できるようにする。
- 麻酔の前にできれば、血液のデータを得ておくことが重要である。鳥は貧血や脱水に対して判定することが困難な場合があるが、PCVが55%以上であれば脱水を示しており、20%以下であれば重度な貧血を示している。血糖値が200mg/100ml以下であれば、5%ブドウ糖を投与してやる。
- 手術をする前に、あらかじめ輸液などをすることは、循環器障害や脱水を防止するためにも行うべきである。また術中においてもセキセイインコなどの場合に、15分おきに0.1mlずつ乳酸化リンゲルを場所を変えて筋注することも有効と思われる。
- アトロピンを導入5分前に、原液10倍稀釈液を正確に、0.03mlの割合で投与し、分泌液の流出を減少させる。またそ嚢の液体はできるかぎり、綿棒などで除去しておく。
- 局所麻酔は感覚の鋭い部位、頭部、脚、関節、肛門(これらの部分は刺激に対して、反応がよいので麻酔のモニターに使用される)などの部位に用いられるが、鳥類は特にプロカインに対して毒性があるので、もし使用するとしても稀釈した0.20%プロカインを用いるべきである。通常、大型鳥に用いられ、小型鳥においてはプロカインは禁忌とされている。
- 吸入麻酔剤のフローセンが最も安全と思われる。通常マスクなどで導入されるが、大型鳥などは籠ごとビニール袋などで覆い導入することもできるが、そのような閉鎖した方法は危険でもある。我々はシャーウッドのディスポーサブルシリンジの外筒を改良して使用し、よい結果を得ている。
- 大型の鳥なら気管内挿管はやさしいが、小型鳥にはちょっとした改良が必要である。しかしながら、この操作で鳥が興奮するようなら有害である。特に小型な鳥などにおいては、挿管時の麻酔の濃度の変化には注意を保ち、酸素の量と共に、正確な液量がコントロールできる気化器を使用する必要がある。もし可能であれば、できるだけ挿管することがよい結果を生むと思われる。
- 回復期には、鳥が傷つかない環境が必要で、鳥を暖かくし明るくしておくと回復は早い。我々は回復しにくい小鳥に対しては、ストッキネット(東京衛材)を使用して、頭を除いて全身をその中に入れて保定している。
- 鳥は絶食させないので、麻酔中、麻酔後に嘔吐、逆流など誤嚥性肺炎の原因となりうるようであれば、柔軟なチューブを導入後に食道に挿入してやればよい。液体の逆流はこの管の内腔を通って外に出る。
外科
鳥類の外科においても、一般外科の原理は十分に応用されなければならない。多くの鳥は症状が進んだ状態で手術しなければならないので、不幸な結果が出ても、以後の手術に対して悲観的な見方はすべきではない。
通常、鳥類の外科手術は眼科用の器具が用いられる。その大きさ、組織に対する扱いは同じように、注意を有するからである。止血はもっとも重要で、30gのセキセイインコを例に取ると、血液量は体重の約10%であり、すなわち30gの鳥は約3g(3cc)である。このことは、1ccが約18~20滴であるから、全部の血液量は約54~60滴である。ゆえに約6滴の血液を失うことは約10%の血液を失ったことになり、12滴は20%、17滴は約1/3の血液を失ったことになる。それゆえに、失血を最小限にくいとめる技術が最も重要である。そのためには鈍性剥離および圧迫止血には消毒した綿棒を用いたり、小さい鉗子を用いたり、血管は細い糸(3-0)で2重に結紮することなどがポイントとなる。
鳥は体温が高いから、感染に対して抵抗性があるといえども、手術は全て無菌的でなければならない。そのためには術野の羽を麻酔後に全部引き抜いて(普通5~6週で羽毛が生える)、綿棒にてイソジンアルコールにて術野が消毒される。もし消毒が不完全だと、鳥はその術野を手術後に突ついてしまうことがある。
鳥類の外科には通常、外傷、出血、腹部膨満の原因療法、骨折、あらゆるタイプの腫瘍、眼球摘出術、断脚、断翼、そ嚢切開、などが挙げられる。手術は時間との闘いでもあり、できるだけ早く行う。そのためには、止血をかねた電気メスの使用や、縫合などの場合も一層縫合で、連続縫合を行うことなどで時間の節約となる。糸と針は一緒に付いた物を選び、できるだけ組織に対して損傷を与えないようにすることが重要である。我々は5-0のデクソンを使用している。
我々の経験では、抜糸を鳥類に行った経験はない。鳥自身がついばんでしまうと思われる。外科手術を受ける鳥すべては24時間前には入院されていなければならない。術前の鳥はできるだけストレスを与えないようにしなければならない。
鳥にガーゼ等を使用するときは、不必要にこすったりしてはならない。また不必要に多く消毒液を用いて鳥を濡らすと低体温の原因ともなる。
覆い布には我々は、滅菌したセロファンを使用している。これら術野及び鳥の動きがよく見えるからである。これらを使用する場合はヒーティングパットの上に、古いフィルムを置き、その上に鳥をテープで保定してさらにその上にセロファンの覆い布をかけている。すると鳥は上下にはさまった状態となり暖かさが保てる。術中は熱ランプなどの保温方法は好ましくない。
術中はいかなる場合も酸素を切らさないことが重要である。電気メスは組織への損傷をできるだけ避けて、決して黒こげにしないこと。また頸部の手術、例えば頸静脈、頸動脈、気管、食道などの部位には使用しないこと。
止血にはまた、硝酸銀棒やスポンゼル(山之内製薬)などが表面の止血には応用される。術後には通常は、抗生物質は応用されない。保温に気を付けながら、鳥が術野をついばまないように鏡など自分が写し出される環境を避け、必要ならばエリザベスカラーを付ける。


